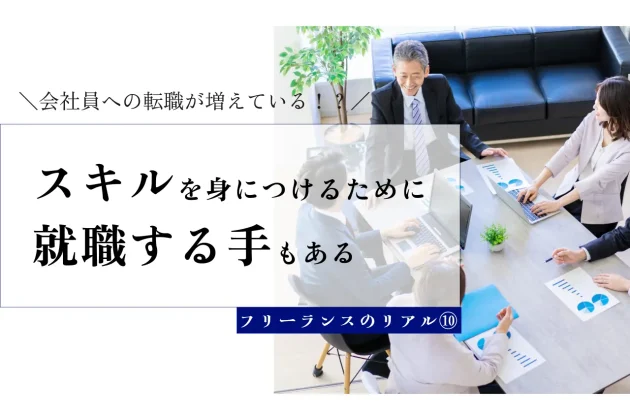ビジネス書の70%以上は、ライターが書いている
ぼくはもともと、出版社で雑誌の編集者をしていたのですが、独立後(2001年)はおもに、「ビジネス書のライター」として、本づくりに携わっています。著者に取材をして、著者の思い、考え、ノウハウ、エピソードを聞き出して、文章にまとめる「裏方」の仕事です。これまでに、200冊以上、執筆のお手伝いをしてきました。
本づくりにおいて、プロのライターを使うことは特別ではなく、日常的です。ぼくの肌感覚だと、ビジネス書の70%以上は(もしかしたらそれ以上?)、ライターが関わっている気がします。
ライターを起用すれば、「書くのが不得意な方」や「書く時間がない方」にも出版のチャンスが生まれますし、ライターを介すことで、文章に客観性が保たれたり、「著者だけでは思いつかないアイデア」が引き出されたりすることもあります。
「ライターが書いている」=(イコール)「著者は書いていない」ということではない、とぼくは思っています。たしかに、実際に手を動かし、物理的にキーボードを叩いているのは、ライターです。でも、「手を動かしていない」という理由だけで、「これは著者の本ではない」「著者は書いていない」と批判するのは、短絡的ではないかな、とぼくは思うのです。
ぼくの仕事は、あくまでも「聞き書き」であって、著者に「成り代わっている」「すり替わっている」のではありません。コンテンツを持っているのは、あくまで、著者です。
ぼくが書いた原稿は、基礎や土台のようなもの。その土台の上に、著者や編集者が加筆修正を施してさらに積み上げ、丁寧に磨き上げてから、本が完成します。
大阪城をつくったのは豊臣秀吉ですが、実際に建てたのは城大工(宮大工)ですよね。城大工や宮大工の力を借りたからといって、「大阪城は秀吉が建てたわけではない」とはならないはず。本づくりも同じではないかな、と。
映画『ジョーズ』は、スティーヴン・スピルバーク監督の作品ですが、脚本を書いたのは、ピーター・ベンチリーと、カール・ゴッドリーブの2人です。スピルバーグが書いたわけではないけれど、それをとがめる人はいないと思います。
ビジネス書も、同じ。分業・協業によって完成します。
本は、人手をかけてつくるものです。原稿は、みんなで書き上げるものです。著者、編集者、ライター、校正者といったプロフェッショナルがチームを組み、それぞれが専門性を発揮する。工夫をする。知見を出し合う。その結果として、読者の心に響く良書が生まれます。
著者と、縦ではなく横の関係を築く
ぼくのことを、「ゴーストライター」と呼ぶ人もいます。
今から8年ほど前(2011年)、ある出版記念パーティーの席で、名刺交換をした女性からこんなことを言われました。
「ようするに、藤吉さんは、ゴーストライターってことですよね。ゴーストライターは、存在しないことが前提ですよね? どうして、いつまでも裏方に甘んじているのですか? 書く力があるのに、どうして、その力を自分のために使わないのですか? 人の文章を書いて、何が楽しいのですか?」
ぼくは別に、「裏方に甘んじている」つもりはなくて、むしろ、「裏方ウェルカム」です(笑)。
ぼくが持っている書く力を、著者と読者のために使う。ノウハウを持っている人(著者)と、ノウハウを知りたい人(読者)の間に「文章」を使って橋をかけるのが、ぼくの役割です。
ぼくにとって、表に出るとか、出ないとか、主役とか裏方とか、どっちでもいいことです。
おそらくこの女性は、著者とライターを「上下関係」で捉えていたのだと思います。「ライターは立場が弱い」と。
これまで、100人以上の著者とお仕事をさせていただきましたが、ぼくはただの一度も、「立場が弱い」と思ったことも、「下に見られている」と思ったこともありません。
なぜなら、ぼくが知る著者は、ひとりの例外もなく、
「ライターは、本づくりのパートナーである」
と認め、ぼくの立場を尊重し、ぼくの意見に耳を傾け、縦ではなく「横の関係」で接してくださっているからです。
「守護霊」という意味でのゴーストライター
ぼく自身、この仕事をはじめた当初は、「ゴースト」と呼ばれることに抵抗があったのも事実です。ゴーストって、なんとなく、うしろめたい響きがありますからね。
でも、今は違います。
「藤吉さんは、ゴーストライターですよね」と言われたら、「はい、そうです!」と胸を張って答えることができます。ゴーストと呼ばれても、肩身の狭い思いをすることはありません。
自分の仕事に、多少なりとも自信が持てるようになったから、自分にしかできない役割を見つけたから、呼び名や肩書きは、もはや何でもOKです。
ぼくは、特定の宗教を持たないので、「霊」のことはよくわかりませんが、ゴースト(霊)は、「悪い霊」ばかりではないと思うのです。ぼくが「ゴースト」を名乗るのであれば、人を呪い恨む呪縛霊や浮遊霊ではなくて、著者や編集者を支えて守る、「守護霊」でありたい。
ぼくが身につけてきた書く力を、呪いの力にするのではなくて、人を励まし、支え、元気にするために使う。それができたら、「ゴーストライターって、かっこいい存在だよね」とぼくは思うのです。